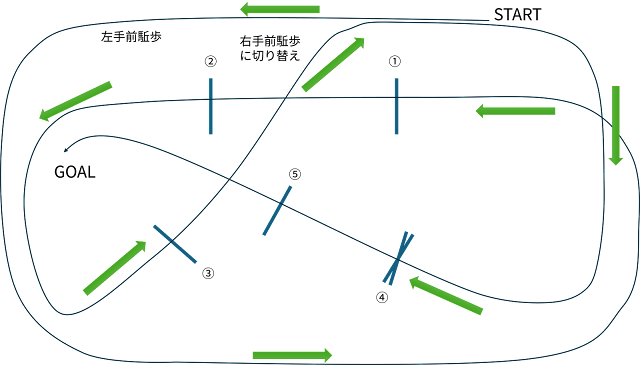235鞍目(初級障害)今週も不穏馬 リベンジ
先週暴れられた馬に再度ヒット。今日はうまく駈歩まででき、思いのほか良いサスペンションの駈歩をすることに気づきました。以下、備忘録。 速歩 立つときに 前寄りにならない ように、かつお尻を軽く浮かす程度の柔らかさを意識する。 駈歩 内方脚の予備動作 が重要。 外方を引くのは後、しかも10㌢ほど 微妙にしか引かない。この順番大事。馬体の内を軽く押さえておいて馬の姿勢を正し、「今から駈歩行きますよ」の雰囲気出して、外方脚をほんのわずか引けば、馬のエネルギーを余計な方向に出力させずに済む。 ムカついて跳ねているわけではなくて、その馬の特性上、他の馬よりも駈歩しやすい姿勢の要求が辛いだけ。 内方脚の予備動作は他の馬でも汎用性がありそうなので、今度からデフォルトで使用してみたいと思います。